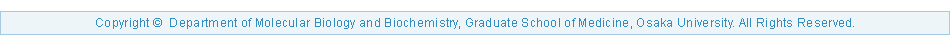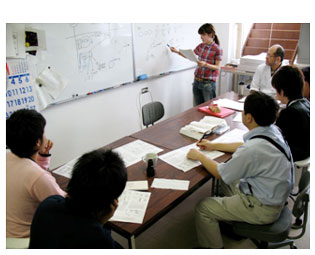平成7年5月に神戸大学の大学院修了後、広島大学の菊池先生の助手として採用していただきました。広島大学ではラボ立ち上げ時から、菊池先生を中心に、小山助教授、私、岡崎(現岸田)想子に加え、臨床科からの大学院生(檜井、池田、村井)も一丸となって、低分子量G蛋白質Rasの標的蛋白質RalGDSやRGLの機能解析に取り組みました。Rasによるコロニー形成能がRGLで抑制されたり、今となっては定量PCRが確立されたため、あまりやらなくなってしまいましたが、これらの分子の局在をノザンブロットできれいに出せたときに妙にうれしかったのを今でも覚えています。空調の効きが悪く、しばしば流し込む前にSDS-PAGEのゲルが固まってしまうのには閉口しましたが。その後のGSK3結合蛋白質検索をはじめとするWntのプロジェクトが、ここまで大きく発展するものとは予想していませんでした。その後の多くの大学院生との研究体験を含め、この広島大学での経験は私にとって、大変得がたい貴重なものだったと感じています。
平成19年2月に鹿児島大学の医化学分野に異動し、研究室を運営すると言う立場を頂くことができました。ラボの窓からは、錦江湾を見渡すことができますが、鹿児島のシンボル桜島は残念ながら見えません。昨年5月には桜島は15年ぶりの大きな噴火があり、降灰がひどく驚きました。現在でも駐車している自動車の窓はすぐに灰で汚れてしまいますので、きれい好きの人には大変です。灰を詰めて捨てるための袋が市役所から配布されるという経験もしました。鹿児島大学では生化学の授業を入学して間もない教養課程の学生に行うカリキュラムなので、カドヘリンで有名な小澤先生と一緒に学生講義を担当しています。講義で生化学に興味を持った学生に対しては、ラボに勉強に来るように働きかけを行ったところ夏休み等を利用して、幾人かの学部生が出入りするようになりました。研究体制については、私と助教(以前からおられる方と岸田想子)に加えて、歯科と薬剤部から大学院生にきていただくことができましたので、ようやく動き始めたというところです。
さて、現在どのような研究を行っているかについて、簡単にご紹介したいと思います。鹿児島で研究室を構えるにあたって、疾患の発症や病態に関わるシグナル伝達について解析が進んでいない分野が有れば、これまでに未経験の分野であっても積極的に取り組みたいという気持ちで機会あるごとにいろいろな先生方に相談した結果、歯科や精神科グループとの共同研究を始めることにしました。歯科とは口腔腫瘍におけるWntシグナルの作用についての解析を進めています。精神科とは、遺伝性の舞踏病の原因遺伝子の機能を解明するため、相互作用する分子の探索を進めています。各種の精神神経疾患領域においては、遺伝学の手法を用いてある程度原因遺伝子が判明していても、発症の機構が十分には判明していないものが、まだかなりあるということを知りましたので、神戸大学や広島大学で学んだ「物質的基盤をもとに生命現象を理解しようとする」やり方で、新たな領域に活路を見出そうと奮闘中です。